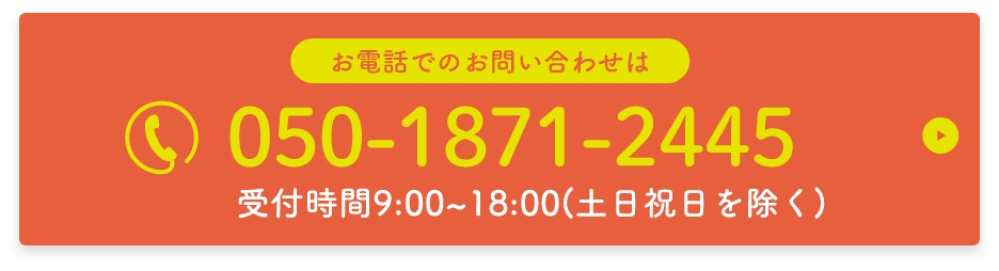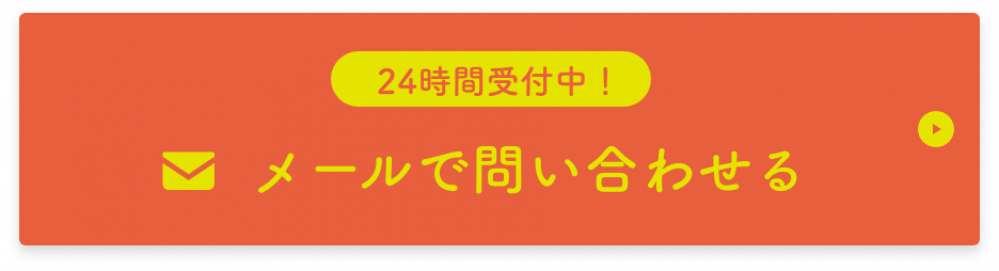沖縄の不動産管理会社が“地域一番”になる方法とは?

不動産管理会社にとって、最大のテーマは「空室をどう埋めるか」です。
賃貸経営において入居率の低下は、そのままオーナーの収益悪化につながり、管理会社にとっては信頼を失う大きなリスクとなり、管理契約がなくなる要因にもなります。
現在、多くの管理会社はポータルサイトやWEB広告に掲載することで入居者募集を行っています。もちろんこれらは必須の集客手段ですが、同じプラットフォームに競合他社も多数掲載しているため、差別化は難しく広告費だけが増大するケースが少なくありません。
特に那覇・浦添・北谷といった人気エリアでは競争が激しく、単純な情報掲載だけでは他社に埋もれてしまいます。そんな状況で注目されているのが 「地域密集戦略」 です。これはランチェスター戦略の基本原則に基づき、「一点集中で地域一番を取る」アプローチ。
管理物件をひとつのエリアに集中させ、のぼり旗・管理看板・3Dマスコットエア看板、さらに統一キャラクターを活用することで、地域全体を自社色で染め上げる。これにより「このエリアならあの会社」と強く認知され、入居者・オーナー双方から選ばれる存在になるのです。
この記事では、沖縄の不動産管理会社が“地域一番”になるための具体的な方法を、事例・戦略・実践ノウハウを交えて徹底的に解説します。
目次
Ⅰ. はじめに
Ⅱ. 沖縄の不動産管理市場と地域戦略の必要性
Ⅲ. ランチェスター戦略を不動産管理に応用する
Ⅳ. のぼり旗で地域をジャックする
Ⅴ. 管理看板で“信頼”を可視化
Ⅵ. 3Dマスコットエア看板で話題化
Ⅶ. 統一キャラクターブランディングの可能性
Ⅷ. 成功事例(仮想・匿名)
Ⅸ. コストとROIの比較
Ⅹ. まとめと行動提案(CTA)
Ⅰ. はじめに
沖縄の賃貸市場は、他県と比べても独自性が強い市場です。観光産業が盛んで外国人居住者も多く、さらに本土からの移住希望者も増えています。その一方で、物件管理のクオリティや入居募集の方法には差があり、空室率の高さに悩むオーナーも少なくありません。
この背景には、沖縄県の持ち家率が全国で最も低いという統計データがあります。総務省統計局が公表している「令和5年住宅・土地統計調査」によると、沖縄県の持ち家率は42.6%(2023年速報値)であり、全国平均の60.9%を大きく下回ります。この統計は、沖縄が賃貸需要の非常に高い市場であることを示しています。
また、沖縄の物件は台風や湿気への対策として、鉄筋コンクリート造(RC造)が主流です。同調査によると、沖縄県の住宅に占める非木造住宅の割合は96.5%に達しており、全国的にも非常に高い割合です。
管理会社にとって重要なのは「いかに地域での存在感を高め、空室を埋める仕組みを持っているか」です。その答えのひとつが「地域一番化」であり、これは単なる広告戦術ではなく、経営全体の方向性を決める戦略でもあります。
Ⅱ. 沖縄の不動産管理市場と地域戦略の必要性
1.入居希望者層の多様性

沖縄の入居希望者層は、以下のように多岐にわたります。
- 移住希望者(転入者):2023年の沖縄県への転入者数は28,847人、前年から1,232人(+4.5%)増加しており、全国で転入増加率が最も高い地域でした。
- 外国人居住者:2023年末時点で沖縄県の在留外国人数は25,447人にのぼり、パンデミック前から 116%増加 しています。
引用元:Guidable Jobs+1
- その他外国人動向:在留外国人の推計では24,386人とされ、7年間で約1.7倍の増加
引用元:沖縄県公式サイト+15braist.co.jp+15Guidable Jobs+15
- 米軍関係者:英語版Wikipediaによれば、在日米軍及びその家族を含めた人員の70%以上が沖縄に駐留しており、基地系の居住者が多数存在します。
引用元:ウィキペディア
これらに加えて、学生層(那覇市や沖縄市周辺の教育機関の存在)、観光業従事者の移住も含めると、沖縄の賃貸市場は多様なニーズの集合体であることが明白です。
2.ポータルサイト依存の限界と現地視認性の必要性
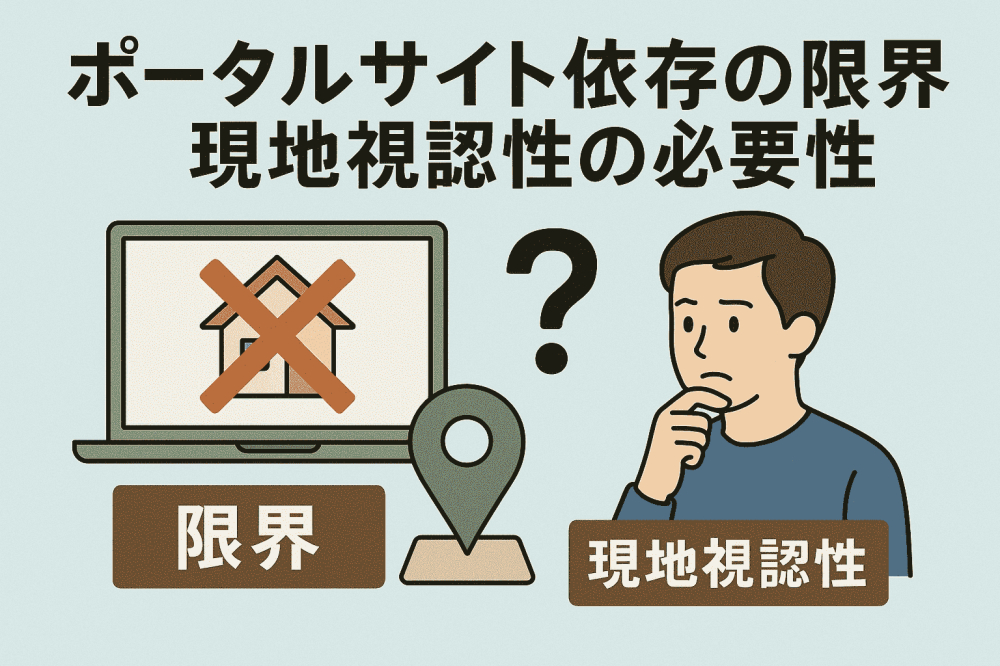
- ポータルサイト掲載数の多さ:那覇市など人気エリアでは、1Kなどの物件が数百件単位で並ぶことが一般化しており、入居検討者には差別化が困難です。
- 車社会の構造:沖縄では、世帯あたり自動車保有台数は全国平均より多く、使用者も高い傾向があります。たとえば、世帯あたり1.7台というデータ(平成30年度)や、中古車の所有量が全国2.3倍という数値があります。沖縄のUターンIターン特化型の転職エージェント | 株式会社レキサン沖縄県公式サイト+1
道路沿いののぼり旗や管理看板は、車移動が主流の沖縄において非常に高い視認性を持ち、入居検討を左右するきっかけになり得ますが、この点を十分に活用できていない管理会社が多い現状です。
これらの課題を放置すると、空室解消やオーナーからの信頼構築、地域でのブランド化という点で競合他社に対抗できなくなるリスクが高まります。
3. 管理会社の競争環境

⑴地場管理会社の規模と存在感
- 中部興産
沖縄県内で最多の管理戸数を誇る管理会社。公式サイトによると、管理戸数は15,000戸以上で、管理戸数・店舗数とも県内トップクラスです。
また、入居率98%、店舗数10店舗という実績も強みとなっています。 - 琉信ハウジング
地場大手として那覇市を中心に展開し、管理戸数8,700戸超、分譲マンション管理は4,497戸を抱えています(2024年3月末時点)。オーナー数は約1,000人。居住用賃貸の管理が主要事業で、那覇市が全体の49%を占めるなどエリア集中型の戦略を採用しています。Zenchin
⑵景況感と経営環境
- 帝国データバンクの調査によると、2024年11月時点で沖縄県の景気DI(不動産業含む)は全国1位。景況感は20ヶ月連続のトップを維持しているものの、人手不足が深刻で、実際の売上・利益に直結しづらい状況とされています。Zenchin+2中部興産+2中部興産+2Zenchin+2TDB
- この背景から、新規参入や業務効率化が難しく、競争はますます厳しくなっていると推測できます。
⑶空き家状況との関連
- 沖縄県の空き家率は全国と比べて低く、直近20年間で10.0%~10.4%の間で推移していますが、空き家戸数そのものは約16,000戸(30%増)と増加傾向です。特に名護市では空き家率が14.9%と県内で最も高い値となっています。
引用元:沖縄振興開発金融公庫
-
空き家の増加は管理会社にとっては対応案件の増加機会ともなり得ますが、管理体制や業務リソースの面で十分に対応しきれる業者は限られる可能性があります。
⑶沖縄における不動産管理会社の競争環境まとめ
|
項目 |
現状 |
|
大手地場管理会社 |
中部興産:15,000戸超、入居率98%、店舗10店/琉信ハウジング:賃貸8,700戸超 |
|
市場構造 |
数社が優位を占めるが、中小管理会社も多数存在すると推測 |
|
景況・経営環境 |
景気DI全国1位だが、人手不足が業績に影響 |
|
空き家動向 |
空き家率は低め(10%前後)だが、戸数は増加傾向、地域差あり(名護市:14.9%) |
4. 課題のまとめ

沖縄の賃貸市場は、移住者・外国人・学生・観光業従事者など多様な入居ニーズを抱えており、転入人口の増加や外国人労働者の拡大といった統計データからもその傾向が裏付けられています。しかし、ポータルサイトに掲載される物件数は膨大で差別化が難しく、さらに沖縄特有の車社会では現地視認性の高い旗や看板の活用が十分に進んでいない現状があります。
加えて、県内最大手の中部興産(管理戸数15,000戸以上、入居率98%)や琉信ハウジング(賃貸管理8,700戸超)が存在感を放ち、景気DI全国1位という追い風がある一方、人手不足や空き家増加といった課題も顕在化しています。つまり市場は「拡大と課題」が同時進行しており、競争環境は一層厳しくなっているのです。
このような環境下で中小管理会社が大手と同じ土俵で戦うのは現実的ではありません。必要なのは、限られたリソースを活かし「特定エリアを徹底的に押さえる」戦略です。
そこで有効なのが ランチェスター戦略 です。弱者の戦い方として「一点集中」を掲げるこの戦略を応用することで、
- 管理物件が集中するエリアを のぼり旗・管理看板でジャック
- 入居者や地域住民の頭に「この街といえばこの会社」と刷り込む
- オーナーに対して「この会社は地域で一番強い」と直感的に伝える
といった差別化が可能になります。
Ⅲ. ランチェスター戦略を不動産管理に応用する
1. 弱者の戦略:一点集中で勝つ

経営学で有名なランチェスター戦略は、戦力が劣る「弱者」が強者に勝つための戦い方を体系化したものです。
地域一番戦略無料資料ダウンロード
大手不動産管理会社のように管理戸数や店舗数で圧倒的な規模を誇る企業に、中小規模の会社が同じ土俵で挑んでも勝つのは困難です。
そこで重要なのが「弱者の戦略」= 一点集中 です。
広くエリアを網羅するのではなく、特定の地域やターゲットにリソースを集中投下し、その場所で圧倒的に認知される存在になる。これこそが中小管理会社が大手に対抗できる唯一の戦い方です。
2. 地域密集の実践
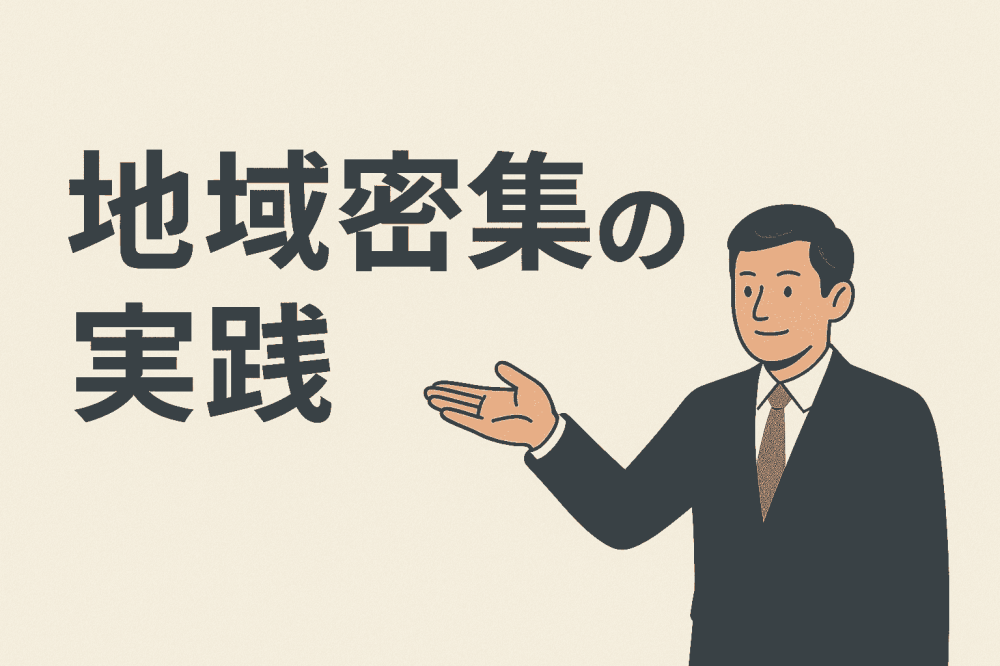
具体的にどう「一点集中」を実現するか。
- のぼり旗の集中設置
管理物件が並ぶ通りに「入居者募集中」ののぼり旗を統一デザインで設置すれば、通行人やドライバーの視覚に繰り返し刻まれます。 - 管理看板の統一展開
駐車場や建物外壁に同じデザインの管理看板を掲げることで、「この街の物件は〇〇不動産が管理している」という印象を地域住民に与えます。 - ブランドカラー・ロゴの徹底活用
統一カラーやロゴを徹底して使えば、街そのものが広告媒体となり、視覚的な「ジャック」が実現します。
これにより、地域の人々は日常生活の中で自然にその会社を認知し、結果的に「この街=この会社」という認識が刷り込まれていきます。
Ⅳ. のぼり旗で地域をジャックする
1. 物件前のぼり設置の基本
課題
- ポータルサイトには数百件単位で同条件の物件が並び、入居者から見れば「どの会社も同じ」に映る。
- 沖縄は車社会のため、現地での視認性が入居検討の決め手になりやすい。
解決策(のぼり旗設置)
- 管理物件すべてに「入居者募集中」ののぼり旗を設置。
- 通り沿いに同じ旗が並べば、地域全体が「自社の管理エリア」として印象づけられる。
効果(ランチェスター戦略の観点)
- 繰り返し視認されることで「この街=この会社」という刷り込みが生まれる。
- 入居希望者に「管理が行き届いている安心感」を与える。
- 地域密集によって、大手に対してもエリア単位で“圧倒的な存在感”を構築できる。
2. 統一デザイン+物件別要素
課題
- バラバラなデザインではブランド認知につながらない。
- 入居者は「Wi-Fi無料」「ペット可」など、自分に合った条件を即座に知りたい。
解決策
- ブランドカラー・ロゴを統一した旗を全物件で使用。
- 物件ごとの特長はサブ要素で追記。
効果
- ブランド力と実用的訴求を同時に実現。
- 入居希望者の記憶に残りやすく、問い合わせ動機を高める。
- ランチェスター戦略で重要な「一点集中による認知の独占」を可能にする。
- 店舗前で地域一番を示す
課題
- 数字での裏付けがなければ、オーナーから「信頼できる会社」とは認識されにくい。
解決策
- 店舗前に「管理戸数◯◯戸」など客観的実績を掲示したのぼりを設置。
- 夜間はライトアップしてランドマーク化。
効果
- 入居者・オーナー双方に「地域で一番信頼できる会社」という印象を与える。
店舗自体が“地域のシンボル”となり、ランチェスター戦略のゴール=地域No.1を体現できる。
Ⅴ. 管理看板で“信頼”を可視化
1. 管理看板の役割
課題
- 看板がないと「本当に管理されているのか」と入居者が不安を抱く。
- オーナーからも「管理会社の存在感が弱い」と見られるリスクがある。
解決策
- 物件ごとに「管理会社名」「連絡先」を明記した看板を掲示。
効果(ランチェスター戦略の観点)
- 「管理物件が街中で繰り返し目に入る」状態を作ることで地域密集効果が生まれる。
- 入居者には安心を、オーナーには信頼を提供できる。
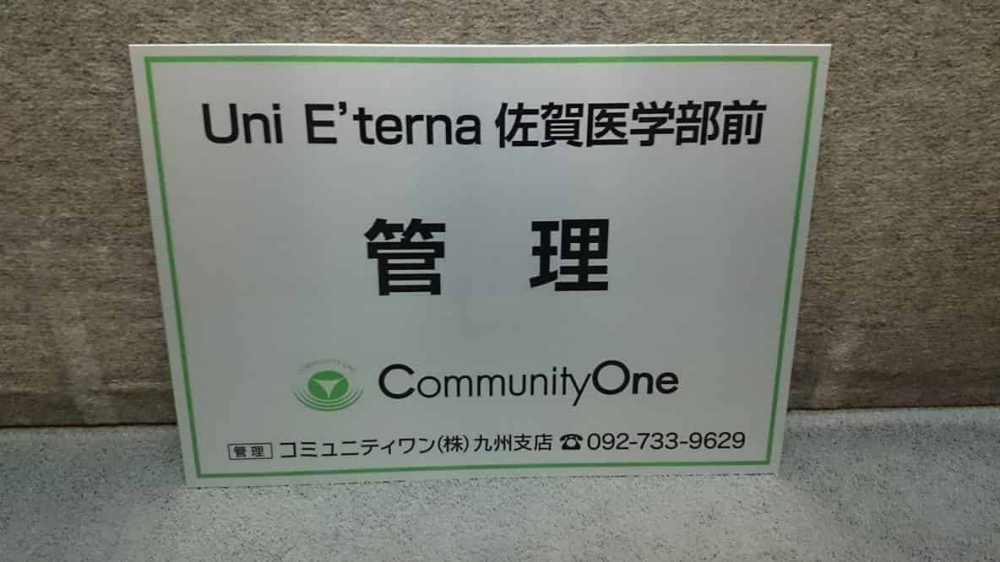
2. デザイン統一の効果
課題
- 看板のデザインがバラバラでは「地域での存在感」が分散し、ブランド認知が進まない。
解決策
- 全物件で共通のデザイン・カラーを採用。
効果
- 「この街は〇〇不動産が管理している」という統一感が生まれる。
- ランチェスター戦略で言う「一点集中の支配感」を街全体で演出できる。

3. 管理会社の営業メリット
課題
- オーナー営業では「戸数」や「入居率」だけでは差別化できない。
解決策
- 「弊社は全管理物件に統一看板を設置し、地域での認知を独占しています」と提案。
効果
- 他社が持たない“地域での可視的シェア”を証明できる。
- 弱者の戦略=「一点集中」でオーナーの信頼を勝ち取る。

Ⅵ. 3Dマスコットエア看板で話題化
1. アイキャッチ効果
課題
- 中小管理会社は広告予算で大手に勝てない。広域での露出は非効率。
解決策
- 店舗やイベントに3Dマスコットエア看板を設置し、地域で圧倒的に目立つ存在になる。
効果(ランチェスター戦略の観点)
- 一度見たら忘れない“視覚的独占”を狭いエリアで作れる。
- 地域での知名度を効率的に獲得し、弱者の「一点突破」を実現できる。

2. かわいい統一キャラの力
課題
- 管理会社は「固い」「親しみがない」と思われがち。
解決策
- 沖縄文化をモチーフにしたキャラクターを作り、旗・看板・ノベルティにも展開。
効果
- 「キャラ=会社」という認知が広がり、地域住民から親しみを持たれる。
- ブランドの象徴として、地域密集戦略の軸になる。
3. スポーツチームの事例から学ぶ
課題
- 管理会社は「応援される存在」になるのが難しい。
解決策
- プロスポーツチームがマスコットで地域浸透を図るように、管理会社もキャラを前面に押し出す。
効果
- 「街に根付くシンボル」として浸透し、ランチェスター戦略でいう“地域制圧”を実現。

Ⅶ. 街をジャックして地域No.1へ──管理会社の成功シナリオ
※下記の3つの事例は実績ではなく、弊社の提案による仮説成果です。
1. 那覇市の管理会社:10棟の管理物件に統一のぼり・看板を設置
那覇市中心部で管理戸数を伸ばしたい中規模の管理会社。
これまではポータルサイトに頼る集客が中心で、空室期間が長期化していました。
そこで取り組んだのが 管理物件10棟すべてに統一デザインののぼり旗と管理看板を設置 する施策。
街を歩けば、どこでも同じ色とロゴが目に入る状態を作り出しました。
結果、入居希望者の来店時には「街のあちこちで御社の旗を見かけた」と言われることが増加。ブランドの存在感が強まり、空室期間は従来より平均30%短縮。オーナーからも「任せると決まりが早い会社」という評価を得ることに成功しました。

2. 宜野湾市の物件:外国人向けに英語表記を追加
米軍基地に近いエリアで管理していた物件。
これまでは「For Rent」と簡単に英語表記する程度で、外国人入居率が伸び悩んでいました。
そこで新たに、管理看板やのぼり旗に英語表記を追加。
「Wi-Fi Free」「No Key Money(礼金なし)」など、外国人が気にする条件を分かりやすく伝えました。
すると、基地関係者やその家族からの問い合わせが増加。オーナーからは「今まで外国人対応は難しいと思っていたが、工夫ひとつで入居率が変わる」と高く評価され、外国人入居率は前年より20%アップしました。

3.学生街の管理会社:大学周辺でマスコット旗を集中展開
大学近隣で物件を多く持つ管理会社。
学生募集のタイミング(春の新学期前)に合わせ、大学周辺の管理物件にマスコット入りの旗を集中展開しました。
キャラクターは学生に親しみやすいデザインを採用。通学路に旗が並び、自然と「このキャラの不動産会社=学生向け」という認識が広がりました。
SNSでも学生が「かわいい旗の会社で部屋探しした」と投稿するようになり、話題性が拡散。結果、学生からの直接来店が増加し、入居率も前年を大きく上回る水準に改善しました。
これらはすべて「ランチェスター戦略=地域密集・一点集中」の考え方を応用した結果です。
旗・看板・マスコットといった“見える仕掛け”で地域に入り込み、入居者・オーナー・地域から選ばれる存在になることが可能であることを示しています。

詳細はお問い合わせください。