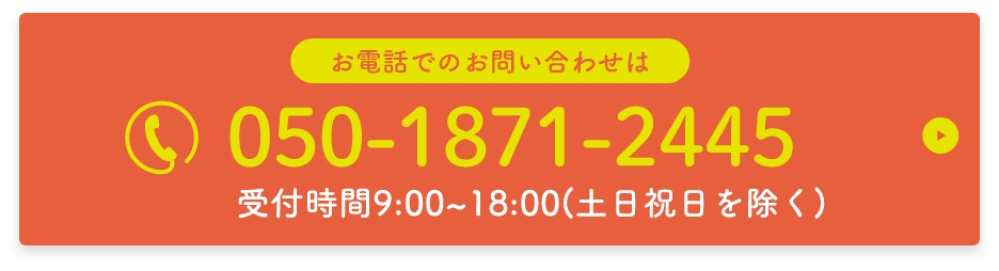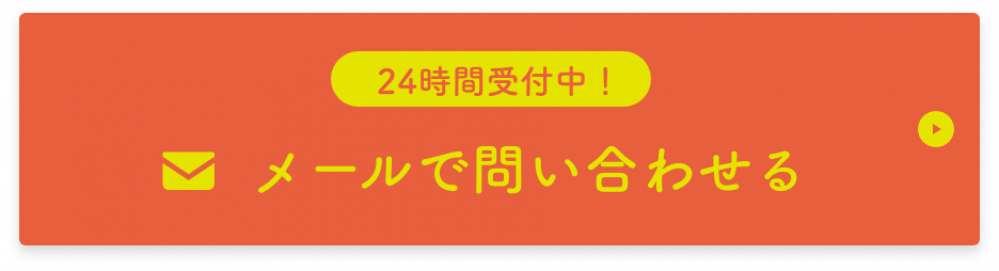景観と調和する広告へ。 沖縄県の屋外広告物条例に即した広告提案

はじめに
沖縄県は、世界に誇る美しい自然と独自の文化を持つ地域です。
その景観を守りながら、街のにぎわいや観光の魅力を高めていくために制定されたのが「屋外広告物条例」です。 この条例は、無秩序な広告設置を防ぎ、建物や自然環境と調和した美しいまちづくりを進めるためのもの。
つまり、“広告を制限するためのルール”ではなく、“地域の価値を守るための仕組み”といえます。企業にとっても、この条例を意識した広告デザインは単なる遵法対応にとどまりません。 地域社会への配慮や誠実な姿勢を示すことにつながり、結果として企業ブランドの信頼性を高める重要な要素になります。
「目立つ広告」から「調和して印象に残る広告」へ。
沖縄の豊かな風景と共存するデザイン発想こそ、これからの時代に求められる広告のあり方です。
目次
沖縄県の屋外広告物条例について
①自家用広告物について
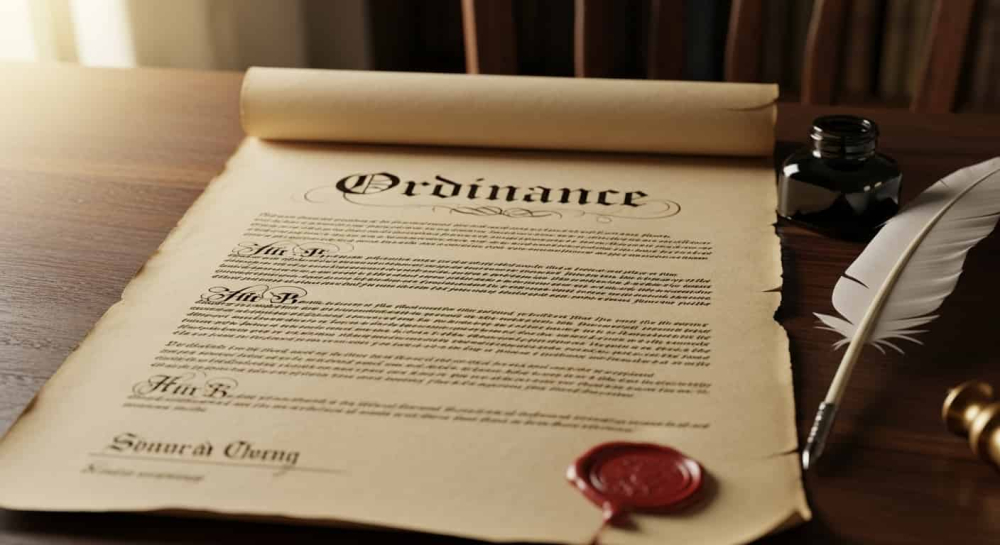
沖縄県では、自社の敷地や建物内に設置する「自家用広告物」について、一定の条件を満たす場合に限り、知事の許可を受けずに表示することが認められています。これは、沖縄県屋外広告物条例第7条第2項およびその施行規則に基づくもので、自社名や店名、商標、事業内容などを示す広告物が対象となります。設置場所は自己の住所や事業所、営業所、作業場の敷地内または建物上に限定され、他人の土地や道路上にはみ出して設置することはできません。表示内容も自社や自店舗に関するものに限られ、他社や第三者の宣伝を目的とするものは自家用広告物に該当しません。
②実際の規制内容

また、広告物の大きさについては、禁止地域(景観・風致地区など)では面積5平方メートル以下、高さ4メートル以下、それ以外の地域では面積10平方メートル以下、高さ4メートル以下であることが条件となります。さらに、景観や風致を損なわないデザインであること、夜間の点滅や過度な照明を用いないこと、構造が安全で落下や倒壊の危険がないこと、道路にはみ出さず通行の妨げにならないことなど、設置方法にも配慮が必要です。これらの条件をすべて満たした自家用広告物であれば、許可を受けずに設置が可能ですが、面積を超える大型看板や敷地外にはみ出す袖看板、景観地区での原色系デザインなどは許可が必要となります。要するに、沖縄県では「自社敷地内で、自社を表示し、10平方メートル以下で、安全かつ景観に調和している広告物」であれば、原則として届出や許可なしで掲示することができるという仕組みです。
|
地域区分 |
許可不要の面積上限 |
高さ制限 |
備考 |
|
禁止地域(景観地区・風致地区・文化財保護区域など) |
5㎡以下 |
4m以下 |
景観保全を目的とした制限。面積を超えると許可が必要。 |
|
その他の地域(一般地域・商業地域など) |
10㎡以下 |
4m以下 |
自社敷地内で設置し、構造が安全で景観を損なわない場合に限る。 |
|
道路や他人の土地にはみ出すもの |
許可が必要 |
― |
自家用広告物の対象外。条例第6条の許可対象。 |
引用元:https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/keikan/1013286/1013287.html
(沖縄県ホームページ)
沖縄県の屋外広告の現状
沖縄県内では、屋外広告物条例に違反する事例が少なくありません。代表的なものとして、那覇市の国際通りで歩道上に無許可の立看板やのぼり旗を設置したケースがあり、通行の妨げや景観の悪化を招いたとして市が是正指導を行っています。
Ⅰ:相次ぐ違反

特に2018年度には約9,700件に及ぶ指導が行われるなど、公共空間の無断利用が問題視されています。また、県管理道路沿いで選挙関連のポスターやのぼり旗が無許可で掲出された事例もあり、公共の道路や電柱、ガードレールといった「禁止物件」に広告を貼り付けたケースでは、県が撤去作業を実施しています。
Ⅱ:企業の責任

これらはいずれも、屋外広告物条例で定められた「許可地域外での設置」「禁止物件への掲出」「安全性・景観を損なう表示」に該当する違反です。こうした事例からわかるように、無許可での広告設置や公共物への掲出は、景観の保全や歩行者の安全確保の観点から厳しく取り締まられており、企業や店舗が広告を設置する際には、条例に基づいた許可申請と適正な管理が不可欠です。条例を遵守することは、地域社会との信頼関係を築き、企業のイメージを守るための基本的な責任といえます。
決して安いとは言えない屋外広告物を事前に決まっている条例を知らないことが理由で無駄にしてしまうことは非常にもったいないです。
沖縄の屋外広告物、現状まとめ
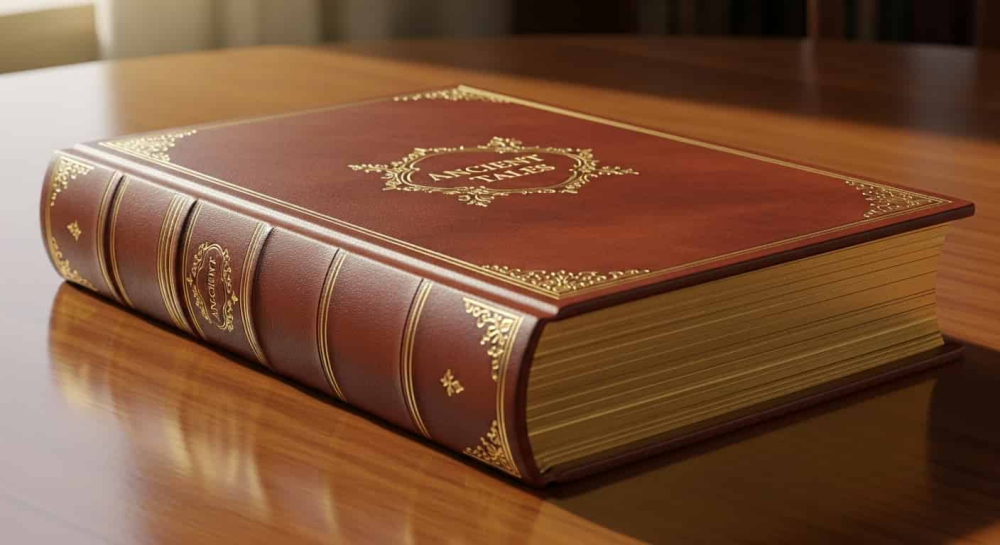
沖縄県の屋外広告物条例は、美しい景観や風致を守るために設けられたもので、企業や店舗が広告を設置する際の基本的なルールを定めています。自社の敷地内で行う「自家用広告物」は、面積や高さ、安全性、デザインなど一定の条件を満たせば知事の許可なしで設置可能ですが、禁止地域や他人の土地・道路への掲出は認められていません。実際には那覇市の国際通りなどで無許可の立看板やのぼり旗が相次ぎ、約9,700件の是正指導が行われるなど違反も多く見られます。条例を理解せずに設置した広告が撤去対象となれば、費用や労力が無駄になるだけでなく、企業イメージの低下にもつながります。したがって、条例を正しく理解し、景観に調和した広告を掲示することは、地域社会との信頼関係を築き、企業のブランド価値を高めるための重要な責任といえます。
条例を守るということ
ⅰ:法令順守は最低限
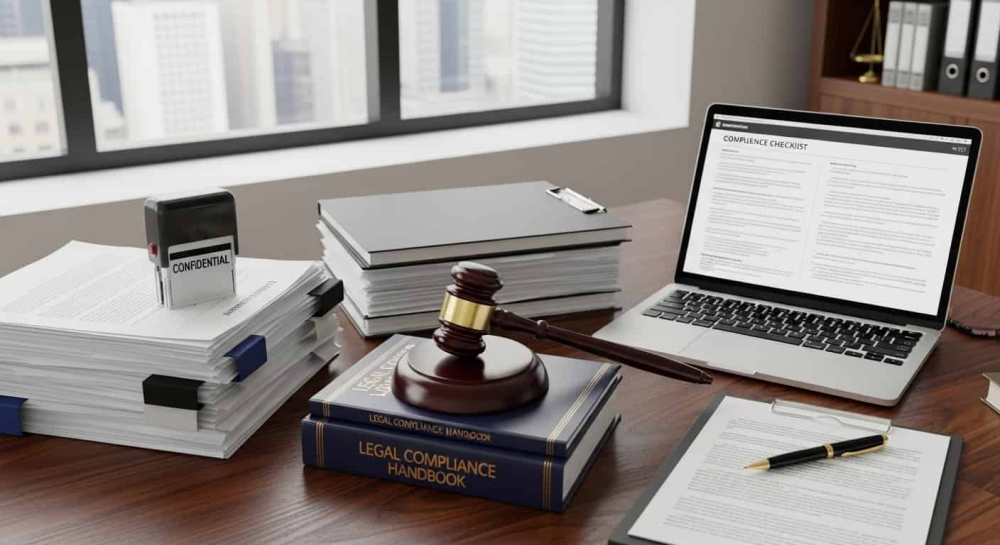
沖縄県の屋外広告物条例は、単に遵守すべき法的ルールではなく、地域社会の一員として企業が果たすべき基本的な責任でもあります。景観や風致を守ることは、沖縄の美しい自然や街並みを未来へ引き継ぐための重要な取り組みであり、広告を掲示する企業にとっても信頼性を高める絶好の機会です。条例を守るということは、「地域と共に歩む姿勢」を示すことであり、企業の社会的信用を築く第一歩といえます。
ⅱ:ブランド価値向上

さらに、景観に配慮したデザインや安全性の高い広告物は、見る人に安心感や誠実さを与え、結果として企業ブランドの価値を高めます。地域の景観を尊重し、調和を意識した広告づくりは、法令順守の範囲を超えて、企業の品格と信頼を可視化する行為です。こうした取り組みを積み重ねることで、「きれいな街に似合う会社」「地域に愛される企業」としてのイメージが自然と浸透していきます。つまり、沖縄県の屋外広告物条例を守ることは“当たり前の基準”であると同時に、企業が長期的にブランド力を育てていくうえで最低限の要素なのです。
条例に即した屋外広告戦略

⑴ 景観と調和するデザイン
沖縄県の屋外広告物条例では、景観や風致を損なわない広告物の設置が求められています。これを企業戦略に取り入れることで、単なる規制遵守にとどまらず、地域に溶け込むデザインによってブランド価値を高めることができます。たとえば、観光地では海や空を連想させるブルーやベージュ系の配色、自然豊かな地域では木目やグリーン系を取り入れるなど、周囲の環境と調和したデザインが効果的です。景観に配慮した広告は、地域住民や観光客に好印象を与えるだけでなく、「地域を大切にする企業」という信頼感を育みます。
⑵ 許可制度を踏まえた持続的な広告
条例に基づく許可制度を理解し、計画的に広告を設置することも重要です。自社敷地内での自家用広告物を活用すれば、一定の条件内で許可不要の範囲で効果的なPRが可能です。また、設置後も定期点検や清掃、更新を行い、倒壊・劣化・色あせなどによる違反を防ぐことが求められます。これにより、法令順守と安全性を両立しながら、長期的に安定した広告運用が実現します。条例を戦略的に活かすことで、地域と共に成長し続ける「持続可能な広告活動」が可能となり、企業の社会的信頼をさらに強化できます。
具体的な屋外広告物提案
ⅰ:敷地内で条例を守る


こちらの巻き上がらないのぼり旗は沖縄の強風に適したのぼり旗です。
また、高さも沖縄県の条例基準を満たしている広告物になります。
ⅱ:より景観を保つ

この七変化のぼり旗は普通ののぼり旗とは違い、自由自在に形が変更できるのぼり旗になっています。そのため、条例範囲内であれば、より地域の景観に近いのぼり旗にすることができます。
また、こちらの広告物も条例の範囲内の高さになっております。
まとめ
沖縄県の屋外広告物条例は、単なる規制ではなく、美しい景観を守りながら地域と共に成長していくための大切な仕組みです。企業にとっても、この条例を理解し遵守することは社会的責任の一部であり、地域から信頼されるブランドづくりにつながります。特に、自社敷地内での自家用広告物を活用し、面積や高さ、デザインなどの基準を守ることで、許可不要の範囲でも十分に効果的なPRが可能です。
また、沖縄特有の自然環境や強風などを考慮した広告物の選定も重要です。たとえば、巻き上がらないのぼり旗や形状を調整できる七変化のぼり旗などは、条例基準を満たしつつ安全性と景観調和を両立させる優れたアイテムです。こうした工夫は、景観を損なわずに企業の魅力を伝える手段として有効であり、「地域を大切にする企業」という印象を強めます。
沖縄の自然と文化に寄り添いながら、景観と調和する広告を掲げること。
それが、これからの時代に求められる“企業のあり方”であり、
持続可能な広告活動を実現するための第一歩となります。
詳細はお問い合わせください。